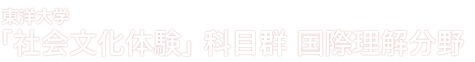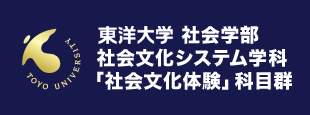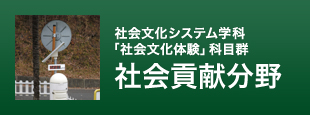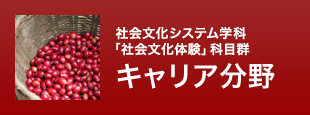受講生の体験記(2018‐19年度履修)
佐 野 真 太(社会文化システム学科)

【日常から離れる】
国際理解分野の授業を履修することで、日常では考えられないような体験ができました。例えば、イスラーム教徒が生活する家でホームステイをしたり、エビの養殖池に入ってエビを手づかみで収獲したりしました。また、都市部から車で2時間もかかる村で村人にインタビュー調査も行いました。これらは、たとえ観光目的でインドネシアを訪れてもなかなか体験することができないものではないでしょうか。
以上のように滅多にできない体験からだからこそ、私たちが見る視点も日常とは変わってきます。インドネシアで暮らす人々が普段見ている世界を、かれらと生活を共にすることで、身近な視点から垣間見ることができるのです。
最後に、2年間の履修を終えて、現地での体験から学んだことは貴重でかけがえのないものだと感じています。そして、これが今の自分の知識欲に繋がっています。この後この国際理解分野を履修する学生には、自分以上の学びを得てほしいと心から願っています。
受講生の体験記(2018‐19年度履修)
矢 野 真 奈(社会文化システム学科)

【成長の実感】
2年間の国際理解分野の活動を通して、とても成長できたと感じ、自分に自信が持てるようになりました。
私は、大学に入学したばかりの頃、高校生の頃の怠惰な生活を反省し、大学4年間はいろいろなことに挑戦することを目標にしました。1年生の時の私は、英語はほとんどできないし、たいした調査もしたことがなかったので、こんな私がインドネシアでフィールドワークなんてできるのだろうかと思っていました。実際にインドネシアに行き、フィールドワーク調査や、インドネシアの大学で行った英語を用いたディスカッションやプレゼンテーションを経験することができて本当に良かったと思います。この経験があったことで3年生の時には新しく自分の関心を見つけ、積極的に動くことができました。
そしてなにより、私はインドネシアという国が大好きになりました。この経験がなければ、インドネシアという国に2回も行くことも、ムスリムの方々とも話すことは無かっただろうし、理解もしようとも思わなかったと思います。未熟な私たちを引率し、調査方法から調査の楽しさまでご教授してくれた先生方に感謝を申し上げます。
受講生の体験記(2018‐19年度履修)
長 谷 川 翼(社会文化システム学科)

【No pain, no gain.】
私が本講義に参加した理由は「社会文化システム学科の目玉であるし、この学科にいるからには受講してみよう」という程度のもので、決して立派な理由ではなかった。
そんな本講義を通して成長したと感じる点を2つあげる。1つは「気づく」力である。調査を行うにつれて、自らの周囲にある小さなことに対しても「どうしてだろう?」「この背景には何があるのだろう?」と考えるようになり、「気づく」力を身につけることができたと感じる。もう1つは「ひとの声に耳を傾ける」力だ。これはただ話を聞くということではない。そのひとの立場や背景にあるものなど、様々なことを汲み取って話を聞くということだ。ここから情報を得ることの大切さ、そしてその難しさを学んだ。
2年間に渡り常に自主的な活動が求められ課題や調査が多く、さらにはインドネシア渡航もあり正直にいえば少々ハードな講義であったと思う。しかしこの講義を終えたいま、自分の人としての成長を確実に感じることができ一切の後悔はない。そしてこの経験はフィールドワークの礎を築く上での大きな財産となった。
受講生の体験記(2017‐18年度履修)
坂 井 美 咲(社会文化システム学科)

【関わる、知る、伝える】
私が国際理解分野の授業に出会ったのは大学1年生のときでした。履修自体は2年生からできる授業なので、当初は先輩や先生方にお世話になりながら、インタビュー調査やプレゼンテーションを見学、時には一緒に調査、発表もさせていただきました。この授業を通じて、座学では習っていた質的調査を、実際に自分の足を使って調査地へ赴き、お話を聞かせて頂くことで実践することができ、社会学を学ぶ上でとても有意義な経験を早いうちからすることができました。
さまざまな人からお話を聞く技術はもちろんですが、それだけではなく、この授業で私に身についたのは自分の意見を発信する技術でもありました。プログラムの一環で日本ではもちろん、インドネシアでもプレゼンテーションをする機会があります。たくさんの先生に支えられながら英語での発表から質疑応答、インドネシア学生との交流に必要となるスキルを養い、時には失敗もしながら仲間と切磋琢磨してきました。
人とうまく関わること、自分と異なるバックグラウンドを持つ人のことを知っていくこと、そして自分の意見、主張を的確に伝えること…国際理解分野で学んだこれらの技術は、これから社会に出る上で必ずどんな仕事でも必要になるものであると私は思っています。まだまだ未熟でありますが、この授業に出会ったことで自分を磨けたことを嬉しく思うと同時に、すべてを支えてくださった仲間、そして先生方に感謝でいっぱいです。
受講生の体験記(2017‐18年度履修)
山 口 桃(社会文化システム学科)

【新しい世界】
私がこの社会文化体験演習・国際理解分野に入って本当によかったと思うことは、大きく2つあります。
1つは就職活動で話のネタになること、2つめは自分の知らない世界を知ることができたことです。まず就職活動において「エビの研究をしていた」ということはかなりインパクトが強く、面接官の方々に興味を持っていただき、自己PRの時間が多くとれました。もちろん、これは私が体験演習に対して3年間(1年次は自主参加)本気で取り組んだことが要因であると考えています。日本やインドネシアにおけるインタビュー形式の調査や文献での調査、インドネシアに実際に訪れるなど、それなりにハードな内容の演習であるとは思います。
内容がハードでありながら、この体験演習を続けてきた理由は、新しい世界を知ることが楽しいからです。他の調査テーマもありましたが、私は3年間ずっとエビについて調査することを選び、築地市場やエビの養殖場などに訪れ、インタビュー形式の調査を行いました。調査のなかで、今まで意識していなかったエビを生産する人々の社会や問題を知り、生産から消費までに関わる人のつながりに感動しました。そしてこの経験から、自分から積極的に話しかけるなど知らない世界に飛び込むことが私の長所だと知ることができました。知らない世界と出会うことは、私を成長させてもくれました。これからの大学生活で、何が好き、何がやりたいかわからない方もいると思います。だからこそ、この体験演習で新しい世界と出会ってみてください。エビに興味があるなしは関係ありません。きっと人生を大きく変える出会いが待っています!
受講生の体験記(2016‐17年度履修)
丹 野 凪 彩(社会文化システム学科)

【かけがえのない宝物】
私がこの授業を履修しようと思った理由は2つあります。1つ目は、プレゼンテーションをする機会が多いこと、2つ目は専門の先生の元で、国内調査と国外調査を行えることです。元々人前で話すのは苦手だったのですが、経験を積む中で、徐々に苦手を克服し、最終的には多くの人の前や英語でプレゼンテーションを行えるようにまでなりました。また、私は何事にも積極的に取り組むようになり、狭かった自分の世界を広げていくことの大切さを学ぶことができました。
国内調査では、私は日本で働くインドネシア人実習生の暮らしについて、インタビュー調査を行いました。文献には書かれていない事実を自分たちの調査によって知ることが出来たのは、大変やりがいを感じることができました。実際フィールドに出て調査を行う中では、自分と向き合う機会が何度もあり、大きな壁にぶつかることもありましたが、振り返ると、それ以上に得られたものが多かったです。様々な人と出会い、知見を広めながら、自分の生き方について考えられるようにもなりました。
このプロジェクトは、エビを通して、日本とインドネシアのつながりについて考えることが目的です。スーパーで買い物をしてエビを見たとき、回転寿司のエビを食べるとき、様々な場面で、調査を通して出会ったインドネシアの人々を思い出します。私たちの身近なところの裏側で、世界の人々と深くつながっている。調査を行ったこの2年間は、私の人生において、かけがえのない宝になりました。
受講生の体験記(2016‐17年度履修)
関 田 世 理 奈(社会文化システム学科)

【エビから学んだもの】
私は2年間国際理解分野に所属し、エビを通して日本とインドネシアのつながりを学びました。
このプロジェクトに参加した当初は、日本とインドネシアのつながりを学ぶ上で、「エビ」が調査対象であったことに疑問がありました。しかし、実際にインドネシアに訪れ、現地の方々への聞き取り調査やフィールドワークを行うことで、日本人の生活とインドネシアの人々の生活のつながりをみることができました。普段何気なく消費しているモノから、世界とのつながりがみえたことにとても衝撃を受けました。そして、どこか自分からは遠く感じていたグローバル化を身近に感じました。
また、エビを育て収穫し、加工するまでの一通りの行程を見学することで、エビが食卓に並ぶまでには、多くの人が関わっているということを思い出させてくれました。モノを消費することは簡単ですが、モノを消費するまでには、様々な人の労働の上に成り立っていることを忘れてはならないと、フィールドスタディを通して思いました。
私はこの2年間で得た、知識や学び、気付きを大切にしていきたいです。
受講生の体験記
元 原 孝 大(社会文化システム学科)

【広がる視野、変わる価値観】
私は、古着のグローバル化に関しての研究プロジェクトで、いかに自分の考えが狭かったのか、また物事に対して深く考えていなかったのかを気づくことができた。そのようなことを気づかせてくれたのは、やはり国内調査、海外調査である。
私はプロジェクトに入る前は、グローバル化の社会文化的側面に関する問題に興味を持っていなかった。特にテーマであった古着とグローバル化の社会文化的な問題に対してはこれまで考えたこともなかった。しかし、この研究プロジェクトは私にこれらの問題に対して興味を持たせてくれた。
私は2年間調査をし、多くの外国の方々と出会うことで、多様な文化や価値観を知ることができた。今までの私は、なるべく人に関わらないように生活をしていた。しかし、このプロジェクトを通じて、私は、外国の方々と出会うことで、自分の考えが変化し、様々な人々との会話が楽しいものに変わっていった。私はこの心境の変化に大変満足している。これからも、私は多くの様々な国々人々と出会い、視野を広げ続けていきたい。
Widening and Changing My Perspective
I noticed how my perspective was so narrow that I did not consider things deeply through my domestic and oversea surveys in a research project on the distribution of secondhand clothes.
Before I joined the project, I was not interested in the socio-cultural issues in our world. In particular, I have never thought about secondhand clothes and the socio-cultural issues of globalization. But this research project made me to be interested in these issues.
I became acquainted with a lot of foreign people during two years of survey, and could know a variety of cultures and values. As a result, this experiences have changed my way of thinking and my sense of values―having open-mindedness and enjoying conversation with foreign people though I used to dislike making conversations with people . I feel happy to change my mentality. So I want to continue widening my perspective through meeting many foreign people from now on.
斉 木 駿 (社会文化システム学科)

二年間、私は古着の流通を通して、グローバリゼーションの社会的側面を学びました。調査は日本、マレーシア、タイで行いました。私は、調査中の不測の事態をある程度、予測できるようになりました。私は何度も調査内容を考え直しました。その過程で、何度も本当に知りたいことは何なのかを考え、それを明らかにするためには何を聞く必要があるのか、その答えを得るために適した質問は何かを考えました。何度もこの作業を繰り返したため、報告書を書く際には、調査目的と調査過程をしっかりと理解していたため、班員には論理的に情報を共有することができました。伝える際には、自分の考えを文章化する、簡単な図を作り、わかりやすくまとめることができました。自分の考えをわかりやすく共有するということは昨年度ではできなかったことなので、自信を得ることができました。
この活動を通して自信を持つことができたので、ここでの活動はとても有意義なものになったと思います。
I have studied about the socio-cultural aspect of globalization through the distribution of secondhand clothes for two years. Through the field survey on this theme in Japan, Malaysia and Thailand, I became to able to forecast the progress of survey. For example, when I faced with unpredictable cases during my survey, I reconsidered my research questions many times.
Through this process, I repeated to ask myself what I really want to know, what I need to listen to, and what is the best suitable question in a given situation. As a result of these repeated questions, when I wrote the research report, I could explain what I was thinking logically to my members of the survey because I really understand the meaning of research questions and the process of my research. For example, I could gather materials―which I acquired in my research―such as document and numeric data in logically and clearly through making graph and table.
Though I could not share my idea logically at the first year of this survey project, I grow up mentally and I could have confidence through these experiences. Therefore, I really appreciate the on-site learning curriculum in my department.
担当教員
| 教員名 | 教員ローマ字 | 職名 | 専門分野 | 関連サイト |
|---|---|---|---|---|
| 寺内大左 | Daisuke Terauchi | 助教 | インドネシア地域研究、環境社会学、国際開発農学 | 詳細ページへ |
| 長津一史 | Kazufumi Nagatsu | 准教授 | 東南アジア地域研究、文化人類学 | 詳細ページへ |
| 山本須美子 | Sumiko Yamamoto | 教授 | 文化人類学 | 詳細ページへ |
| 左地亮子 | Ryoko Sachi | 准教授 | 文化人類学、ジプシー/ロマ研究 | 詳細ページへ |
| 平島(奥村)みさ | Misa Hirashima(Okumura) | 教授 | 文化社会学、比較社会学、比較文化論、映像文化論 | 詳細ページへ |
| 三沢伸生 | Nobuo Misawa | 教授 | 中東社会経済史 | 詳細ページへ |
参加学生
3年生:山本 諒太、石田 彩華、堀江 亮、五十嵐 美雪、倉持 寛毅/2年生:福谷 駿、西村 悠希、三上 和奏、江幡 風花、森田 唯衣花、錦織 優希菜、田中 理恵子、安本 凜々香、梅田 勇輝、小川 雪那、北嶋 莉子、荒井 大和、平井 展人、LING FENGYU